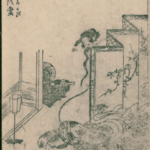「更生」から「懲役」の場へ変質していった「人足寄場」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉜
■現代の組織に通底する変質
1790(寛政2)年、江戸の石川島に設けられた人足寄場は、日本の近代的刑務所の源流となった施設である。明治維新後に石川島監獄署、巣鴨監獄を経て、現在の府中刑務所へと続く日本の矯正施設の出発点としても知られる。
人足寄場設立の直接的な契機は、1782年から1787年にかけて発生した天明の大飢饉だ。この未曾有の食糧危機により、生活基盤を失った「無宿」と呼ばれる浮浪者が江戸市中に激増し、治安を著しく悪化させた。
この深刻な状況に対し、人足寄場は二元的な目的を持って設置された。一つは不穏分子を一掃する治安対策としての「予防拘禁(よぼうこうきん)」。もう一つは、無宿者に職業技術を授け、更生を促すという社会政策的側面、すなわち「仁恵の措置」だ。これは、刑罰後に再び無宿として社会に放り出され、再犯に至る悪循環を断ち切ることを目指したものだ。
設立は、寛政の改革を主導した老中・松平定信の構想を土台とし、時代劇でも知られる火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)・長谷川平蔵(宣以)が建言し、実行責任者となった。
平蔵は、労働に対する賃金支払い(作業有償制)、釈放後の生業資金とするための強制積立(元手の制)など、当時としては極めて先進的な処遇制度を導入した。さらに、幕府からの支給だけでなく、製品販売や地代といった自己収入で財政を賄う手腕を発揮。平蔵は幕府からの借入金を銭相場への投機に用い、その差益を予算に充てるという大胆な手法も用いている。
長谷川平蔵の情熱と先進的な制度設計から始まった人足寄場だが、設立から30年を経た頃から、その実態は大きく変質する。この変質は、対象者の「質」と「量」の変化によって不可避的に進んだ。
まず、1820(文政3)年以降、施設は江戸払以上の追放刑の受
そこで幕府は、有罪者を追放せずに寄場に収容し、職業訓練を通じ
さらに、天保期には飢饉の影響で収容者が激増した。設立当初は140~150人程度であった収容者が、400~600人余りにまで膨れ上がったのである。
丁寧な更生指導の余裕が失われる中、苦役である油絞りが導入され主要な労役となると、施設はさらに懲役場に近い実態となった。法的には最後まで「保安処分」の施設であったが、その実態は近代的自由刑の原初的形態へと変化していったのである。
人足寄場が府中刑務所へと繋がる系譜は、現代の組織運営に重い教訓を投げかける。
長谷川平蔵が掲げた「仁恵」の理念は、対象者の増加や変化、そして苦役の導入という「量」と「質」の圧力によって、その根幹を揺るがされた。人足寄場の変遷の歴史は、社会的使命という理念と、効率や利益の優先という現実との狭間に立たされたときに、組織が直面する根源的なジレンマを如実に示している。崇高な理念を掲げることは容易だが、それを維持し続けることの困難さ――この教訓は、現代の企業や公共機関にとっても、決して他人事とはいえない。
- 1
- 2